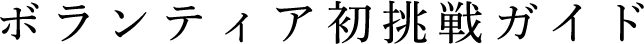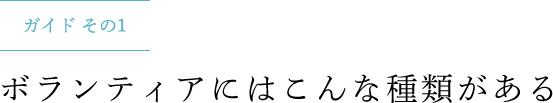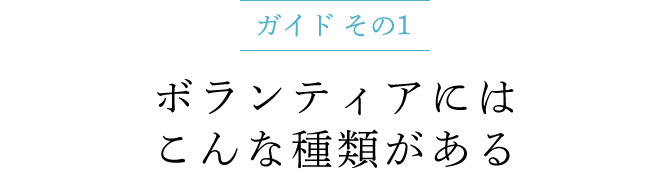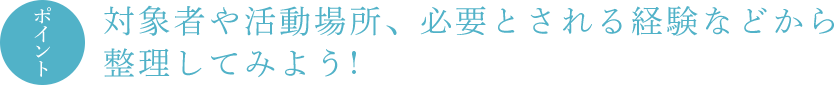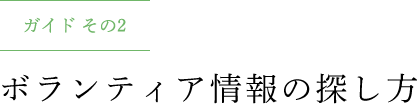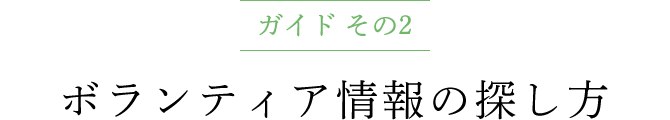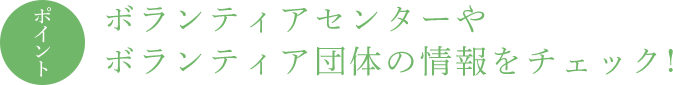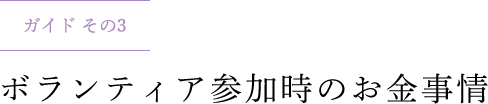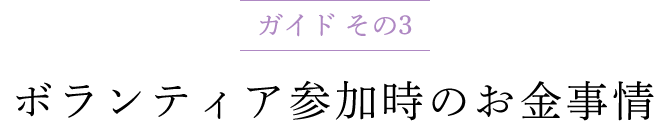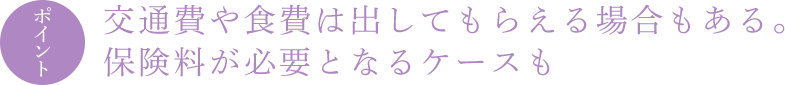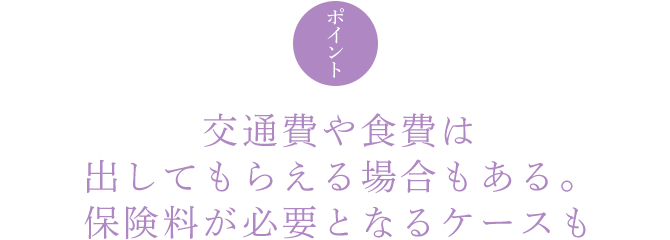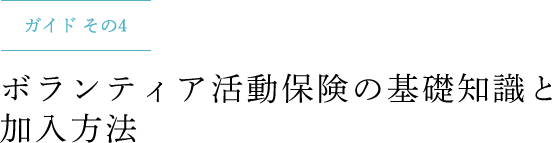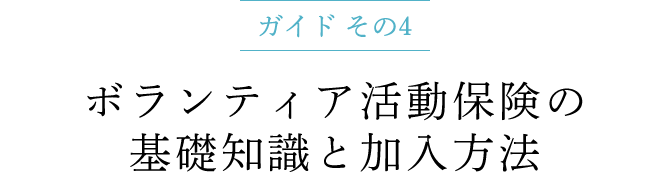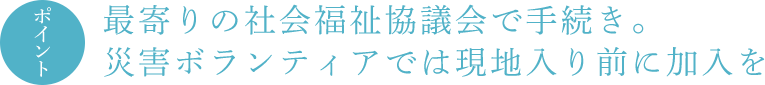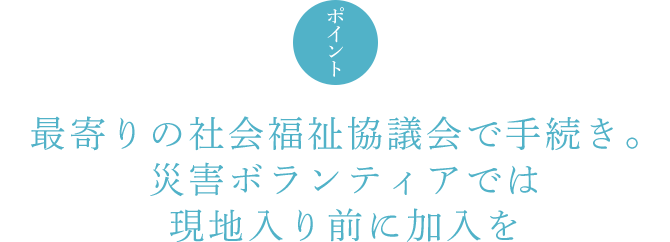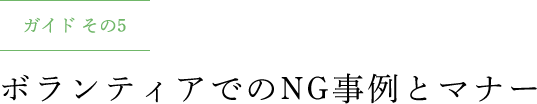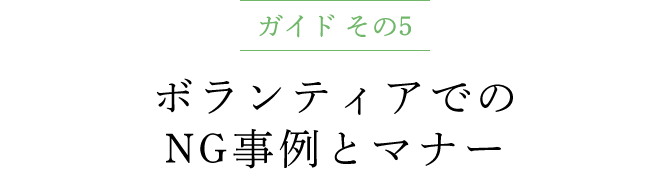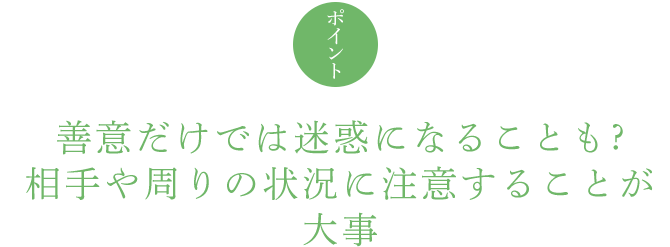無償で、他人や社会のため自発的に行う活動のことをボランティアと呼びます。
災害時に炊き出しやがれきの撤去を行ったり、増加する訪日外国人のために通訳をしたりなどタイミングごとに必要とされるボランティアから、地域住民の生活に密着したボランティアまで、種類は様々です。スーパーボランティアとも呼ばれる方の活躍を見て、自分もあんな風に人の役に立ちたいと考えた方も多いのではないでしょうか。
大和ネクスト銀行は預金を通じてSDGs (Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標) の達成に向けて貢献しています。そこで、社会貢献に興味のある方のために、ボランティアについて最低限知っておきたい5つの情報をまとめてみました。

何でもいいからボランティアを始めたい ! という状態だと、漠然とし過ぎていて逆に始めづらいかもしれません。ボランティアにはどのような種類があるのか、まずは知っておきましょう。
| 種類 | 対象・場所 | 内容 | 必要とされる経験 |
|---|---|---|---|
| 地域ボランティア | 地域全般 |
|
|
| 社会福祉ボランティア | 障がい者 高齢者 |
|
|
| 国際ボランティア | 訪日外国人 各国の地域・住民 |
|
|
| 災害ボランティア | 被災地 |
|
|
| スポーツ・文化 ボランティア |
イベント会場 |
|
|
ボランティアにかかる期間や、必要とされる参加頻度についてはそれぞれです。月1回程度やイベント単位で募集しているものから、できれば月~金毎日というものまでありますので、自身が無理せず参加できるものを選びましょう。
これまでの経験、資格などは必要なく、やる気さえあれば参加できるというボランティアが多いものの、外国語ができれば国際ボランティア、手話ができれば手話通訳、楽器ができれば演奏会のボランティアなど、自身の得意な分野、経験を活かせるボランティアもあります。
ちょっと自信がないなという人のために、あらかじめ講習会を開いてくれるボランティアもあるようです。

どんなボランティアが自分に向いているかわからないという方も、まずは具体的にどのようなボランティア活動があるのか情報収集をしてみましょう。
ボランティアセンターなど相談窓口で探す方法
地域ごとに社会福祉協議会が運営するボランティアセンターがあり、ボランティアの募集情報が確認できます。ボランティア講座の開催、ボランティア保険の案内などもあるので、ボランティアを始めたいと思ったら利用してみるのも良いでしょう。
- ボランティアセンターの利用手順
- 1.最寄りのボランティアセンターを確認します。インターネットでは、「市区町村名+ボランティアセンター」などで検索して探します。
- 2.ボランティアセンターのウェブサイトで活動内容や所在地を確認します。募集情報がある場合もありますが、全ての情報が掲載されているとは限りませんし、特に初めての場合は窓口で直接相談してみると良いでしょう。
- 3.ボランティアセンターに赴き、自身に合った募集情報がないか確認してみましょう。
ボランティア団体に登録しておく方法
外国語が得意な方であれば通訳ボランティアの団体、スポーツが好きな方はスポーツボランティアの団体など特定の団体に登録しておくと、ボランティアの募集情報は自然と入ってくるようになるでしょう。団体に登録することで、すぐに定期的な活動を始められるかもしれません。
- ボランティア団体への登録手順
- 1.「都道府県名+ボランティアの種類名 (通訳ボランティアなど) 」などで検索し、ボランティア団体のウェブサイトを探します。
- 2.登録条件、登録方法などを確認し、問題がなければ手続きをします。
- 3.個別の活動への参加方法は各団体に確認しましょう。
災害ボランティアの場合は ?
災害発生時には災害ボランティアセンターといった組織が開設されます。ウェブサイトやSNSなどで情報を見つけ、連絡をとった上で参加しましょう。ボランティアセンターなどの組織を通さず個人で飛び込み参加をすると、場合によっては迷惑をかけてしまうといったことにもなるので注意が必要です。

ボランティアなので無償で活動することにはなりますが、報酬ではなく経費についてはどうでしょう。特に災害ボランティアについては、ボランティア活動保険への加入が必須となるケースも多くあります。
ここではボランティアに必要なお金についてまとめてみました。
| 交通費 | 1日1,000円までなど上限付きで交通費が支給されるボランティアもありますが、基本は自己負担と考えましょう。 最近では、兵庫県が災害ボランティアに上限20万円までの交通費、宿泊費を助成すると発表するなど、自治体が公費助成をするケースも出てきました。 (2019年3月現在) |
|---|---|
| 食費 | お弁当や食事などをボランティア先が用意するケースもありますが、募集要項に書かれていない限り支給されないと考え、お弁当を持参する、現地で調達するなどが必要です。 |
| 保険 | ボランティア活動中に起こる自身のケガの補償、対人・対物の賠償責任の補償などをカバーしてくれる、ボランティア活動保険。年間350円程度からの保険料が必要です。参加にあたって加入が必須のボランティアもあります。 ※詳しくは「ガイド その4」でご紹介します。 |
「謝礼」が出るケースもありますが、活動にかかる経費以上のお金を受け取ると本来の意味でボランティアとは呼べず (有償ボランティアという言葉もありますが、定義はあいまいです) 、謝礼が出たとしても、上記のような交通費や食費、必要な材料費、準備費代わりのものと考える方が良いでしょう。

ボランティア活動を行う前に加入しておくと安心なのが、ボランティア活動保険です。
ボランティア活動保険とは
ボランティア活動時の偶然な事故により自身がケガをした場合や、相手にケガをさせてしまい損害賠償責任を負った場合などに補償される保険です。
補償される活動の条件は、「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」や「社会福祉協議会に届け出た活動、もしくは委託された活動であること」などです。災害ボランティアなどは、参加にあたって加入が必須条件となっている場合もあります。その際、基本タイプの補償範囲に加えて地震、噴火、津波によるケガも補償される天災タイプに加入することが一般的です。
例えば、実際に多い事故である「転倒」でケガをした場合、補償金として通院保険金は日額4,000円~、手術保険金は32,500円~をボランティア活動保険により受け取ることができます。そのほか、死亡保険金、入院保険金、賠償責任保険金 (対人・対物) などの補償もあります。
ボランティア活動保険への加入方法
最寄りの社会福祉協議会の窓口にて加入申込書・保険料払込用紙をもらい、必要事項を記入し、金融機関にて保険料を振り込みます。その後、加入申込書・保険料の支払証明書を社会福祉協議会の窓口に提出します。
災害ボランティア参加時にも、必ず現地入り前にお住まいの地域で加入しておきます。現地で加入できる場合もありますが、迷惑をかけてしまう可能性もあるため、控えた方が良さそうです。
加入時の手続きは本人である必要はなく、加入者から委任を受けた代理人でも問題ありません。また、団体で申し込みをする場合は、加入者の名簿を作成して持参すれば、代表者が手続きを行うこともできます。
![]()

| Aタイプ | Bタイプ | |
|---|---|---|
| 基本タイプ | 350円 | 510円 |
| 天災タイプ (基本タイプ+地震・噴火・津波) |
500円 | 710円 |
補償内容はプランによって異なります。
2019年4月現在の全国社会福祉協議会ホームページによると以下の補償内容となっています。
| Aプラン | Bプラン | |||
|---|---|---|---|---|
| ケガの補償 | 死亡保険金 | 1,040万円 | 1,400万円 | |
| 後遺障害保険金 | 1,040万円 (限度額) | 1,400万円 (限度額) | ||
| 入院保険金日額 | 6,500円 | 10,000円 | ||
| 手術保険金 | 入院中の手術 | 65,000円 | 100,000円 | |
| 外来の手術 | 32,500円 | 50,000円 | ||
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 6,000円 | ||
| 特定感染症の補償 | 上記後遺障害、入院、通院の各保険金額に同じ | |||
| 葬祭費用保険金 (特定感染症) | 300万円 (限度額) | |||
| 賠償責任の補償 | 賠償責任保険金 (対人・対物共通) | 5億円 (限度額) | ||
| ケガの補償 | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 1,040万円 | 1,400万円 | |
| 後遺障害保険金 | 1,040万円 (限度額) |
1,400万円 (限度額) |
|
| 入院保険金日額 | 6,500円 | 10,000円 | |
| 手術保険金 | 入院中の手術 | 65,000円 | 100,000円 |
| 外来の手術 | 32,500円 | 50,000円 | |
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 特定感染症の補償 | 上記後遺障害、入院、通院の各保険金額に同じ | ||
| 葬祭費用保険金 (特定感染症) | 300万円 (限度額) | ||
| 賠償責任の補償 | Aプラン | Bプラン | |
| 賠償責任保険金 (対人・対物共通) |
5億円 (限度額) | ||
- ※東京都、京都府、兵庫県など独自プランで対応している都府県もあります

ボランティア参加者、団体、ボランティアを受ける側の人たちなど、ボランティアを始めると新たな人間関係が生まれます。貴重な出会いとなる一方、気を付けないとトラブルも当然起こり得ます。ボランティアならではのマナーや注意点についてまとめてみました。
「ボランティア」だからと軽々しくドタキャン
あくまで自発的、無償でするものだから、自分の都合に合わせればOK。そのような気持ちで参加すると、逆に迷惑をかけてしまうことがあります。連絡もなくドタキャンするのはもってのほか、ボランティア先の都合を考えずマイペース過ぎる行動をしたり、参加できる回数を約束したのに反故にしてしまったりなど、ボランティアだからと甘えた行動はNGです。
ただし、体調が悪い、説明されていた内容と違ったといった状況で無理に続けるのも良くはありません。やめる際にはボランティア先に可能な限り理由を説明した方が、自身の気持ちもすっきりとするはずです。
ボランティアに力を入れ過ぎて家族に迷惑をかけてしまった
インターネット上では、「夫がボランティアにお金を使い過ぎていて困っている」 「家の中までボランティア活動に使われていて、落ち着かない」といった相談が見受けられます。
自分のボランティア活動が原因でなんらかの迷惑をかけることになれば、人のためという理由だけでは納得してもらえません。活動範囲を明確にし、家族など周囲からの理解はきちんと得ておきましょう。
ほかの参加者とケンカしてしまった
ボランティア活動に参加するのはみんないい人たちだろう、と想像されるかもしれませんが、そこは他人同士の難しさ。合う人もいれば合わない人もいるはずです。意見を交わすのは大事かもしれませんが、ただのケンカになってしまうと困ります。
大切なのは、相手の立場になって考えること。また、意見が食い違ってもすぐ冷静になることです。もしトラブルが起こったら、団体の責任者など第三者に相談をしてみましょう。
定年後にやりがいのある活動がしたい、空いている時間を有効活用したい、誰かの役に立ちたい、社会をもっと良くしたい、そんな思いを持つ方たちは、今回の記事を参考に、ぜひボランティア活動に挑戦してみてください。
一方で、ボランティアをしたい気持ちはあっても、活動にあてられる時間がまだない、自信がないという方もいるかもしれません。
外で活動するボランティアでなくても、寄付という形で誰かの力になることも可能です。直接的な寄付だけでなく、預金が支援につながるカタチがあることをご存知でしょうか ?
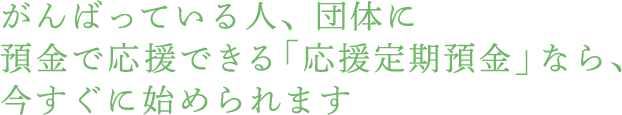
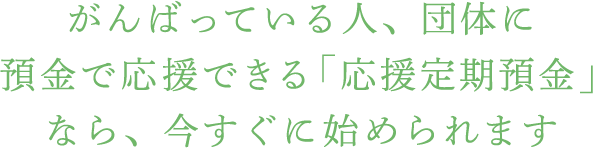
がんばっている人や団体を、預金を通じた寄付という形で支援できるのが、大和ネクスト銀行の応援定期預金。預入残高に一定割合を乗じた金額を、自分が選んだ応援先に大和ネクスト銀行が届けるユニークな預金です。「医療支援」「こどもの自立支援」「障がい者スポーツ支援」など、様々な支援先がある中から、いくつか例を挙げてみました。
-
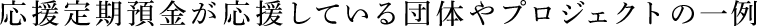
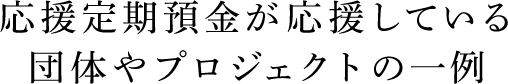
-
-

「長期入院のこどもたち 応援定期預金」 急病により緊急搬送されるなどし、長期入院となったこどもたち。自由に外出できず季節を感じるのが難しいこどもたちのために、夏祭りやクリスマスのイベントを実施。ほぼ寄付により運営されていますが、毎年十分な金額が集まるわけではなく、応援定期預金で応援しています。
-

「児童養護施設を退所する高校3年生 (茨城) 応援定期預金」 保護者のいない児童や虐待されている児童などが生活する児童養護施設。原則18歳までに退所となりますが、頼りになる家族がおらず経済的自立が難しいのが現状です。クルマ社会の茨城県では自動車運転免許証の取得が必須となる職業も。このような厳しい環境で夢をあきらめることなく自立を目指す高校3年生への支援を行っています。
-

「スポーツ用義足で“風を感じる”応援定期預金」 病気やケガで手や足を失ってしまった人たちがスポーツをするためには、生活用義足ではなくスポーツ用義足が必要です。生活用義足は健康保険などで補助されますが、スポーツ用義足には支援がありません。多くの障がい者に新しい生きがいを見つけてもらいたい、スポーツの楽しさを味わってもらいたいという思いから設けられた応援定期預金です。
-
そのほかの支援先や応援定期預金についての詳細は、
以下のページからご覧いただけます。