2025年6月26日
「日本人の家計簿」の最新データ。お金はどうすれば増える ?
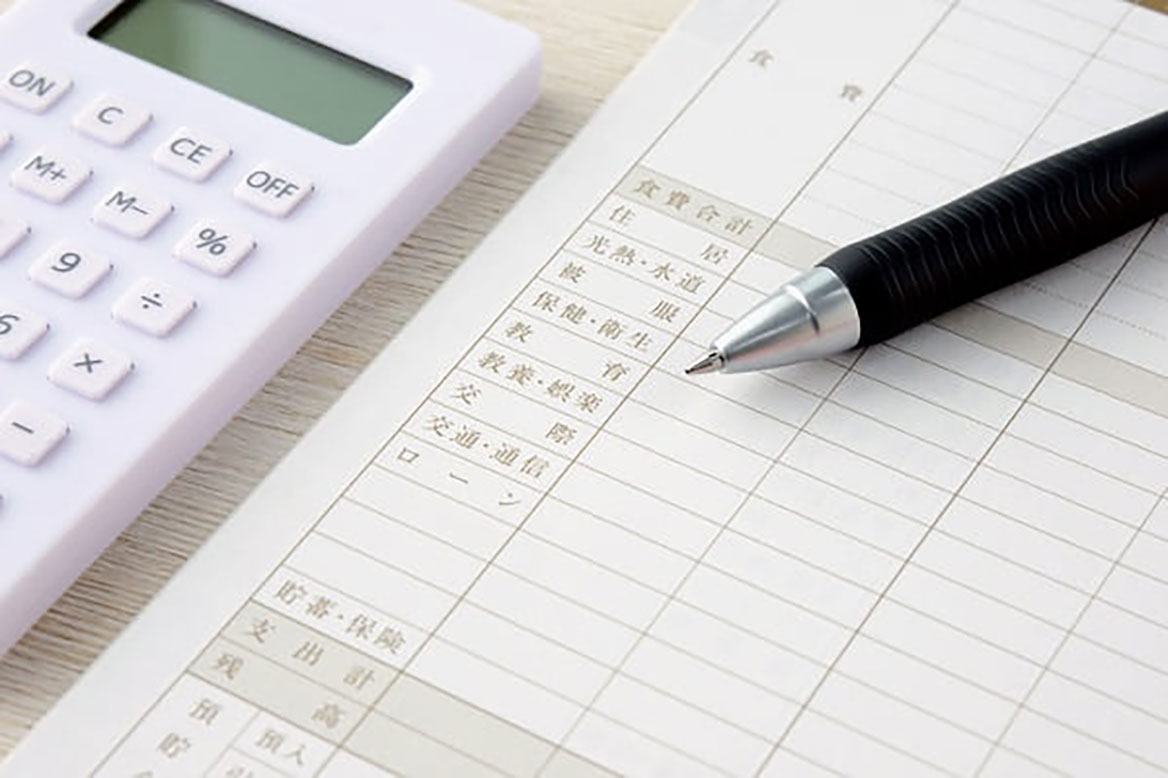
世帯ごとに支出の内容は異なるものの、日本人全体の平均的なデータを知ることは、自分のお金の使い方を見直すうえで有効な手がかりとなる。本記事では、「日本人の家計簿」の最新データを一部紹介しながら、支出の管理だけでなく、「運用」という視点を持つことの重要性についても解説する。
日本人の家計簿の平均値は ?
総務省統計局が公開している2024年の「家計調査」を参照すると、日本人の家計収支の平均値を項目ごとに知ることができる。例えば「食料」の支出を見ると、以下のように1世帯 (2人以上の世帯) の1ヵ月あたりの支出額が確認可能だ (※以下の表は一部を抜粋したもので、実際にはほかの支出項目も確認できる) 。
| 穀類 | |
|---|---|
| 米 | 2,164円 |
| パン | 2,851円 |
| 麺類 | 1,713円 |
| 他の穀類 | 497円 |
| 合計7,225円 | |
| 魚介類 | |
| 生鮮魚介 | 3,289円 |
| 塩干魚介 | 1,072円 |
| 魚肉練製品 | 739円 |
| 他の魚介加工品 | 894円 |
| 合計5,993円 | |
| 肉類 | |
| 生鮮肉 | 6,633円 |
| 加工肉 | 1,501円 |
| 合計8,134円 | |
| 乳卵類 | |
| 牛乳 | 1,324円 |
| 乳製品 | 1,999円 |
| 卵 | 988円 |
| 合計4,311円 | |
| 野菜・海藻 | |
| 生鮮野菜 | 6,202円 |
| 乾物・海藻 | 740円 |
| 大豆加工品 | 1,159円 |
| 他の野菜・海藻加工品 | 1,124円 |
| 合計9,225円 | |
「支出を減らす」=「収入を増やす」 ?
このような「日本人が平均的にどの項目にどれくらいお金を使っているか」といったデータは、支出を見直すうえで非常に参考になる。ただし節約には限界があるため、「家計収支の改善に向けてさらに収入アップしたい」といった考えにたどりつく人も少なくないだろう。たしかに家計簿上「支出を1,000円減らすこと」は「収入が1,000円増えること」と実質的に同義である。
しかし、特に日本企業で働く会社員の場合、外資系企業と比べて能力が給与に反映されにくく、年収が一定の水準で頭打ちになりやすい傾向がある。
節約にも限界があり、収入アップも簡単ではない――そんな状況でこそ活用したいのが「資産運用」だ。給与収入だけに頼るのではなく、資産そのものを増やしていく視点を持つことが、家計の安定や将来への備えにつながっていく。
初心者向けの資産運用の方法は ?
資産運用は、大きく2つの型に分類される。値上がり益を狙う「キャピタルゲイン型」と、保有することで安定した収益を得る「インカムゲイン型」だ。
値上がり益を狙う「キャピタルゲイン型」
キャピタルゲイン型の代表的な運用方法には、株式投資やインデックス型の投資信託などがある。例えば株式を100円で購入し、150円で売却すれば50円の利益が生じる。これがキャピタルゲイン (値上がり益) である。
一般的に株式投資では、個別銘柄を選んで保有することになるが、株価の動きを読むのはプロでも難しい。そのため初心者には、日経平均株価やS&P500などの株価指数に連動する「インデックス型の投資信託」がおすすめだ。
インデックス型の投資信託は、特定の市場全体の平均的な動きに連動して価値が変動する仕組みで、リスク分散の観点からも優れている。
安定した収益を得る「インカムゲイン型」
株式投資もインデックス型の投資信託も、基本的に価値の値上がりを狙った資産運用の手法だ。しかし、経済の先行き不安などが広がった場合、どちらも価値が大きく下落しやすい。こうしたリスクに不安を感じる場合は、保有しているだけで安定した収益を得られる「インカムゲイン型」の資産運用を検討するのも一つの方法だ。
代表的な例として挙げられるのが「外貨預金」である。外貨預金は、円預金よりも金利が高いことが特徴で、外貨を保有し続けるだけで安定的に利息収入を得ることができる。そのため、投資初心者でも取り組みやすく、資産運用の入門として選ばれることも多い。
ただし、外貨預金には為替リスクがある点に注意したい。為替の変動によって、円換算での資産価値が目減りする可能性もあるが、安定的なインカムゲインが得られるため、為替差損が出た場合でも一定の相殺が期待できる。
リスク分散の2つの手法
資産運用には、キャピタルゲイン型とインカムゲイン型の2つの型があることを理解したうえで、投資を始める前に知っておきたいのが「リスク分散」の考え方だ。リスクを抑えながら資産を安定的に育てるには、大きく分けて2つの分散手法がある。
資産の分散
1つ目は「資産の分散」だ。例えば株式投資では、市場全体が下落すると多くの銘柄が連動して値下がりする傾向がある。そのため、株式だけに資産を集中させていると、相場の急落時に大きなダメージを受ける可能性がある。
そこで効果的なのが、異なる種類の資産を組み合わせて保有することだ。「株式+外貨預金」といったように異なる種類の資産を組み合わせておけば、資産全体で見たときに、株式の下落によるダメージを小さく抑えることが期待できる。
時間の分散
2つ目は「時間の分散」だ。投資の世界では「高値づかみ」という言葉がある。ある資産を高値のタイミングで購入してしまうと、その後の下落によって長期間含み損を抱えることも少なくない。
こうしたリスクを減らす手段が、投資時期の分散である。なかでも、一定額を一定の頻度で購入していく「積立投資」は、初心者でも実践しやすく、価格変動の影響を平均化する効果がある。
お金を「働かせる」ことが重要
資産を増やすためには、支出の見直しや収入アップを目指すだけでなく、「お金を働かせること」も大切だ。キャピタルゲイン型とインカムゲイン型、それぞれの特徴を理解し、自分のリスク許容度に合ったバランスで取り組むことで、堅実な資産形成が可能になる。
さらに、リスクを抑えながら長く運用を続けるためには、「資産の分散」と「時間の分散」の考え方が重要だ。自分の資産が市場の変動に過度に振り回されなければ、運用によるストレスや不安も少なくなる。結果として、長期的かつ計画的な投資を続けやすくなるだろう。
(提供:株式会社ZUU)
- ※本ページ情報の無断での複製・転載・転送等はご遠慮ください。
- ※本ページの情報提供について信頼性の維持には最大限努力しておりますが、2025年6月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
- ※本ページの情報はご自身の判断と責任において使用してください。

